

キャリアアップを目指す!
詳しくはこちら

次に、請求書の保存期間を見ていきましょう。
請求書の保存期間は、個人・法人によって変わります。そのため、あなたの状況に合った保存期間をこちらで覚えておきましょう。
個人事業主の場合、請求書の保存期間は原則5年と定められています。
また、個人事業主では申告方法として青色申告・白色申告の2パターンがありますが、どちらも請求書の保存期間は原則5年なので、覚えておきましょう。
しかし、個人事業主の中でも、例外として請求書を7年間保存しなければならない方もいます。
請求書を7年間保存する必要がある方は、課税売上高が1,000万円以上の消費税課税事業者です。
また、保存期間の計算方法ですが、請求書を発行した日ではなく、その年の確定申告期限日の翌日から5年間・7年間などで、こちらも併せて覚えておきましょう
法人の場合、請求書の保存期間は原則7年間です。
大企業・中小企業など会社の規模にかかわらず、保存期間は原則7年間なので覚えておきましょう。
「普通法人等は、前条第1項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第59条第2項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から7年間、これを納税地(前項第1号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
※引用:税務研究会
例外として請求書の保存期間が9年間・10年間の場合もあります。それは、赤字が出てしまった年の請求書です。
平成20年4月1日以降に赤字が発生した年度の請求書は9年間、平成30年4月1日以降に赤字が発生した年度の請求書は、10年間の保存期間があることも併せて覚えておきましょう。
また、法人の請求書保存期間は、事業年度の法人税申告期限日の翌日から7年・9年・10年です。
結論から言うと、請求書は一定の期間、保存する義務があります。
国税庁のホームページには、法人の場合の保管期間についてこのように記載されています。
「法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。
(注1)『帳簿』には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。
(注2)『書類』には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。」
※引用:国税庁
請求書は「信憑書類」として、所得税法・法人税法・消費税法に基づいて、一定期間の保存が定められています。
しかし、請求書の保存は、基本的に受け取った側のみ義務化されているため、発行した側は請求書の保存は義務化されていません。
そのため、会社のルールで請求書の控えを保存していない場合は、受け取った請求書のみ保存しておけば問題はないと言えます。
請求書を保存しなければならないことが分かったところで、次に請求書の保存方法を見ていきましょう。
請求書の保存方法は主に3通りあるので、事前に決めておくことをおすすめします。
請求書の保存方法
・請求書の保存方法①:電子版(データ)
・請求書の保存方法➁:紙
・請求書の保存方法③:マイクロフィルム
ペーパーレス化や電子取引が増えたことで、税務署長の承認が得られれば、電子データで請求書を保存することが認められます。
電子データには、自社で作成したオリジナル電子データや、紙の請求書をスキャナで読み取った電子データなどがあります。
今後、請求書を紙ベースから電子ベースに変更したいと考えている場合は、一度税務署に相談してみると良いでしょう。
従来のやり方として、請求書を紙で保存する方法があります。
請求書を紙で保存する場合はとても簡単にできますが、法人の場合7〜10年間保存し続けなければいけないため、管理が難しく膨大な量の請求書がたまってしまうでしょう。
そのため、請求書を紙で保存する場合は、一定期間の保存が必要な書類をまとめるための、セキュリティ対策を万全にした保管庫などが必要不可欠です。
請求書を保存する3つ目の方法として、マイクロフィルムがあります。こちらも電子データ同様に要件を満たすことで、保存が認められます。
また、マイクロフィルムで請求書を保存できるのは、保存期間の最後の2年間だけです。
例えば、法人で7年間保存する必要がある場合は、最後の年の6年目と7年目のみマイクロフィルムでの保存が認められています。
今回は、請求書の保存期間についてまとめました。
請求書の保存期間は、個人と法人で定められている期間が異なります。
・個人:原則5年間(課税売上高が1,000万円以上の方は7年間)
・法人:原則7年間(平成20年4月1日以降に赤字が発生した年度の請求書は9年間、
平成30年4月1日以降に赤字が発生した年度の請求書は10年間)
そのため、あなたの現在の状況に合わせた保存期間を確認しておきましょう。
また、請求書は「信憑書類」といって、所得税法・法人税法・消費税法などから一定の保存が定められています。
したがって、知らない間に処分してしまったとなると、取引した証明が発行できないなど、大ごとになってしまう可能性も考えられます。
証憑書類の保管に困っている場合はクラウドシステムの導入も有効です。

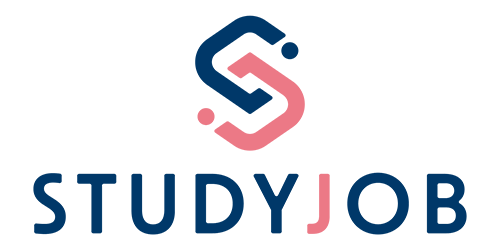
2021年生まれ。 BPOや業務効率化など企業成長のためになることがすき。 特にスタートアップやベンチャーなど新しいことに挑戦している人たちを応援するのが生きがい。 知りたい情報のリクエストも受け付けてます!
SEARCH