

キャリアアップを目指す!
詳しくはこちら

有価証券とは、文字通り証券そのものに価値がある紙面のことです。そのため、譲渡することによって財産的権利を移転することができます。
国税庁では、有価証券の範囲について以下のように規定しています。
| 印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する証券であって、その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものをいいます。
(引用元:有価証券の範囲|国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/09.htm) |
財産的権利の違いによる分類は「物財証券」「資本証券」「貨幣証券」の3つです。
有価証券を広義に定義する場合は「物財証券」「資本証券」「貨幣証券」の三つになりますが、狭義に定義する場合は「資本証券」のみになります。
一般的に有価証券と言えば「資本証券」を指すことが多いでしょう。
具体的には、資本証券は「株券」「債券」「投資信託」を指すので、つぎからそれぞれ詳しく解説していきます。
株券とは、株式会社が出資者に対して発行する証券のことで、出資者(株主)の地位や権利を表すものです。
出資者(株主)は、保有株式の割合に応じて会社経営に参加したり、配当金として企業の利益の一部を受け取ったりすることができます。また、株式会社が成長して株式の価値が値上がりすれば、株券を市場で売却して利益を得ることも可能です。
平成16年に商法改正が行われ、株券不発行制度が認められました。さらに平成21年度からは上場会社の株券が電子化され、上場会社はすべて株券を発行しないこととなりました。株券を発行しないでどのように管理するのかというと、証券会社を通じて「ほふり」と呼ばれる証券保管振替機構に預けることになります。
株券電子化によって紛失や盗難のリスクがなくなるというメリットがありますが、口座管理や本人確認が厳格になるということに注意が必要でしょう。
債券とは、国や企業など(発行体)が資金を調達するために発行する証券です。債券には満期があり、発行体は満期になったら額面金額を債券購入者(投資家)に返済しなくてはなりません。
投資家は、発行体に資金を貸し付ける代わりに、クーポンと言われる利子を受け取ることができます。また、債券を市場で売却する権利を得られるため、購入したときよりも高い価格で売却すれば、売却益(キャピタルゲイン)を受け取ることも可能です。
信託とは、文字通り自分の財産を信頼する人に託すこと。投資信託とは、証券会社や銀行などの受託会社が投資家から資金を集めて、一つの大口の資金としてまとめたものを運用する金融商品です。
運用の成果が出れば、利益が投資家に分配されます。また、投資家は投資信託を売却することで出資した資金を受け取ることもできます。
投資信託で運用された資金は「信託財産」として受託会社によって管理されます。受託会社自身の財産や他の信託財産とは分別して管理されているため、たとえ破たんすることがあっても、信託財産は法的に保護されるということを覚えておきましょう。
金融商品会計基準では、有価証券は原則として時価で評価するという立場がとられています。ただし保有する目的によっては、時価で評価することは必ずしも適切ではないものも存在します。
保有する目的に応じて有価証券を分類したものが、以下の4つです。
ここからは、それぞれの定義と評価方法を解説していきましょう。
売買目的有価証券とは、時価の変動によって売買利益を得るために保有する有価証券を指します。市場の動向を注視しながら短期間で売買するものや、1年以内に満期が到来するものが該当します。
売買目的有価証券として分類するためには、有価証券の売買を業として行っていることが定款に明記されていなければなりません。
〔評価方法〕
期末時価で評価し、評価差額を当期の損益に計上します。
満期保有目的債券とは、文字通り満期まで保有することを目的としている有価証券を指します。満期まで保有することによって、決められた償還金や利払い日には利息を得ることができます。
満期保有目的として分類するためには、①満期日が定められていること、②額面金額による償還が予定されていること、の二つの要件を満たさなくてはなりません。
〔評価方法〕
取得原価で評価します。ただし額面と異なる金額で購入した場合は、償却原価法で評価します。償却原価法とは、取得原価と額面金額とが異なるとき、その差額を満期日に至るまでに毎期一定の方法で取得原価に加算または減算する方法です。
子会社および関連会社株式とは、子会社および関連会社に対する影響力を行使(営業の意思決定をする権利を獲得)することを目的として保有する株式を指します。
子会社および関連会社株式は、短期的な利益を得ることが目的ではなく、会社の成長性を期待して保有するものと言えます。
〔評価方法〕
取得原価で評価します。
その他有価証券とは、上記の3つ以外の有価証券を指します。
〔評価方法〕
期末時価で評価し、評価差額を当期の損益に計上します。
ここまで解説した有価証券の定義と評価方法をまとめると、下の表のようになります。
| 保有目的区分 | 定義 | 評価方法 |
| 売買目的有価証券 | 時価の変動によって売買利益を得るために保有する有価証券 | 時価 |
| 満期保有目的債券 | 満期まで保有することを目的としている有価証券 | 取得原価
(償却原価) |
| 子会社株式・関連会社株式 | 子会社および関連会社に対する影響力を行使することを目的として保有する株式 | 取得原価 |
| その他有価証券 | 上記以外の有価証券 | 時価 |

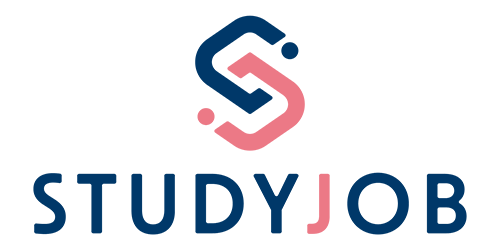
2021年生まれ。 BPOや業務効率化など企業成長のためになることがすき。 特にスタートアップやベンチャーなど新しいことに挑戦している人たちを応援するのが生きがい。 知りたい情報のリクエストも受け付けてます!
SEARCH