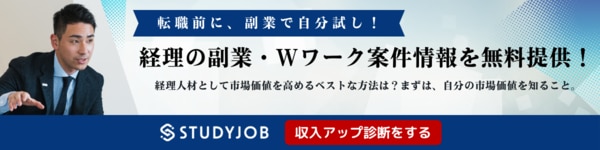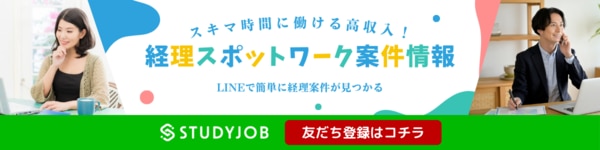【徹底解説】外注費とは?給与や支払手数料との違い、仕訳の注意点
オンラインアシスタント・秘書サービスなら「サポーティア(SUPPORT+iA)」
事業活動を行う上で、自社の業務の一部を外部に委託することもあります。委託先に支払った報酬は、一般的には外注費として計上します。
一見よくある勘定科目・取引内容ですが、外注費の取り扱いには注意が必要です。経理処理の方法に問題があれば、外注費ではなく給与として見なされることがあります。給与と外注費では源泉徴収や消費税などの処理が異なるため、正しい対応が必要不可欠です。
この記事は、外注費の基本的なとらえ方や支払手数料・給与との違い、仕訳における注意点などを解説します。
目次[非表示]
- 1.外注費とは
- 1.1.外注費と支払手数料の違い
- 1.2.外注費と給与の違い
- 2.外注費と税金
- 3.外注費のメリット・デメリットは?
- 4.外注の取引先によって税金の対応が変わる
- 4.1.外注先が法人の場合
- 4.2.外注先が個人事業主の場合
- 5.外注費とインボイス制度
- 6.外注費が給与と認定された場合の影響
- 6.1.消費税・源泉所得税の課税
- 6.2.延滞税・加算税の課税
- 7.外注費が給与認定されないためには
- 7.1.外注費か給与かを判断するポイント
- 8.外注費の仕訳
- 8.1.法人(源泉徴収が発生しない)の場合
- 8.2.個人事業主(源泉徴収が発生する)の場合
- 9.まとめ
外注費とは

「外注費」とは外部の企業や団体、個人と請負契約を結び、業務の一部を委託するときに支払った費用を意味します。
請負契約は仕事を請け負った人が仕事を完成させ、その結果に対して報酬を支払う契約形態です。
例えば、Webコンテンツを作成するために外部のライターやデザイナー、プログラマーなどに業務を委託した場合が外注費にあたります。他にも、オフィスの清掃業務を委託したり、派遣社員の派遣料を派遣会社に支払ったりした場合も、外注費になります。
このように外部の人材に業務委託や発注をすることで、自社にはない技術やノウハウの活用が可能です。また、社内の限られた人的リソースをコア業務に充てることができるため、業務負担の軽減にもつながるでしょう。
外注費は正しく経理処理を行わなければ給与として見なされる恐れがあります。給与とみなされると、源泉所得税が追徴課税されるだけでなく、仕入費用として認められる消費税が否認されたり、延滞金・加算税といったペナルティが課されたりする恐れが大きいです。
そのため、外注費と似た部分のある支払手数料・給与との違いや、どのようなものが外注費として認められるのかを正しく理解する必要があります。
外注費と支払手数料の違い
外注費は前述のとおり、社外の相手に対して業務の一部を委託したときの費用です。このような外注費と混同しやすい支出として、支払手数料が挙げられます。
支払手数料は、公認会計士や弁護士など、専門的なスキルを持った人材に仕事を依頼したときに使用する勘定科目です。
また、パンフレットやノベルティグッズなど、自社の商品の販売促進のためにかかった費用は販売促進費となります。
似ている支出でも性質によって使う勘定科目が異なるため、経理処理を行う際には注意しましょう。
外注費と給与の違い
原則として、外注費は外部委託した場合の報酬、給与は自社の従業員に支払う報酬です。実質的には雇用契約であるのに外注費で計上する・外注費の支払い相手が事業者ではないなどの場合、給与とみなされる恐れが大きいです。
外注費と給与を比較すると、源泉徴収や社会保険料、消費税の取り扱いに大きな違いがあります。
まずは源泉徴収についてです。
給与は源泉所得税を天引きしたうえで支払う必要があります。一方、外注費の場合は原則として源泉徴収は不要ですが、原稿の報酬など一部の支払い(所得税法第204条第1項)については源泉徴収が必要です。
具体的には支払う金額が100万円以下の場合、10.21%の税率が適用されます。
例えば、30万円の報酬を支払ったときには、「30万円×10.21%=30,630円」を預り金として徴収する必要があります。一方で給与の場合は、支払った給与額や扶養家族の人数などで所得税額が決まる仕組みです。
社会保険料についても、外注費の場合は徴収をする必要はありません。一方で給与の場合は加入する保険の種類によって徴収する必要があります。
消費税について、外注費では仕入費用と見なされるため、消費税の支払いも発生します。給与の場合はそもそも消費税がかかりません。
このように外注費と給与は異なる点が多く存在します。外注費として適切に処理されていなければ、税務署から給与と判断されるケースもあるので十分に注意しましょう。
なお外注費と給与の区別で特に注意するべき業種として、建築業と製造業が挙げられます。それぞれの注意点を詳しく解説します。
建築業の場合
建築業では、建物を建てたり工事を行ったりする際に、個人事業主である職人(一人親方)に人工代(にんくだい)を支払うケースが多いでしょう。人工代とは、作業員1人あたりの1日の作業量に対する費用であり、一般的にこの費用は外注費として取り扱われます。
しかし、外注費とみなされるためには、職人自身が事業者である必要があるためご注意ください。雇用契約を結んでいたり、それに近い形で発注元の会社から指揮監督を受けながら仕事を進めたりしていれば、給与とみなされる恐れがあります。
製造業の場合
製造業を営む会社が他社に材料を提供して製造業務の一部を委託する場合、外注費として取り扱われます。商品の製造や加工、組み立てなどの業務を依頼するときに生じる費用が外注費です。
製造業の場合は製造原価に外注費が含まれるため、材料費や労務費などと並んで外注費が大きな割合を占めるケースもあります。そのため適切に処理を行っていなければ、後から税務上の問題が生じる場合もあるので注意しましょう。
外注費と税金

外注費と給与では、税金の計算方法や取り扱いに違いがあります。特に消費税や源泉所得税の計算では注意が必要です。どのような点に気を付けるべきかを解説します。
消費税の違い
消費税は事業者が事業の対価として得る資産などに対して課税されます。そのため、労働者に対して支払う給与はそもそも課税対象となりません。すなわち給与に対して消費税は発生しないのです。
一方で、外注費の場合は事業者がサービスなどを提供したことに対する対価であり、「事業の対価として得る資産」となります。したがって外注費は消費税の課税対象です。
消費税は課税期間中の課税売上から、課税仕入れにかかった消費税額(仕入控除税額)を差し引いて計算します。
外注費は課税仕入れにあたります。外注費を支払う場合は、消費税の対象外である給与を支払う場合と比べて、消費税の納付額が少なくなるでしょう。
源泉所得税の違い
源泉徴収を行う義務がある法人や個人を「源泉徴収義務者」といいます。法人だけではなく、個人事業主も源泉徴収義務者の対象となる点に注意が必要です。
ただし、常時雇用をする人が2名以下で家事使用人への給与の支払いや、弁護士などに報酬を支払っている場合は源泉徴収の義務はありません。
給与の場合は源泉徴収税額表を用いて、給与額に応じて源泉徴収額を計算する必要があります。
一方で外注費の場合、源泉徴収する税率がはじめから決められているため、給与の場合よりも計算方法がシンプルです。支払う報酬額が100万円以下では10.21%、100万円を超える部分は超過部分に対して20.42%の税率で計算を行います。
なお、給与の場合は年末調整が必要ですが、外注費の場合は年末調整が不要です。
外注費のメリット・デメリットは?

外注費は判断が難しい費用ですが、それでも外注費として計上することが多いのには理由があります。ここでは外注費のメリットとデメリットを見ていきましょう。
外注費のメリット
外注費のメリットはいくつかありますが、まず仕事を外注するということにもメリットがあります。
外注する仕事は専門性の高いものも多く、社内で一から教育して技術を身につけたり、人材を育成したりするのはとても大変です。そこですでに専門的な技術を持った人に外注することで、コストや手間を削減することができます。
また煩雑なバックオフィス業務などを外注すれば、会社の本来の業務に集中できるメリットもあるでしょう。
外注費を使うメリットは、金銭的な負担と時間の手間を減らせることです。一つずつ見ていきましょう。
雇用した人に給与を支払う場合は社会保険料の負担が発生します。しかし外注費であれば、業務に対する費用のみで、社会保険料の負担がないため、それだけ支出が減ります。
また外注費であれば、源泉徴収税額の計算は一律です。給与の場合は源泉徴収税額表に沿って、それぞれの給与に合わせて計算が必要になり、時間と手間がかかります。
さらに給与所得者には年末調整が必要です。年末調整は準備から実際の処理までに多くの時間がかかりますが、外注費であればその時間も必要ありません。
外注費のデメリット
もちろんデメリットもあります。仕事を外注する上でのデメリットはコミュニケーションの難しさや継続して仕事を依頼していく難しさを感じることにあるかもしれません。
外注費を使うデメリットは税務面が大きいでしょう。まず外注費と給与の判断が難しいことがあります。外注費のつもりで申告したら、給与とみなされたとなると追加での納税などが必要になります。
また外注費の場合は消費税がかかります。給与であれば消費税の負担はありませんが、外注費は費用の10%は消費税として負担が必要です。さらに外注先がインボイス制度に登録していなければ、仕入税額控除ができません。
外注の取引先によって税金の対応が変わる

仕事を外注するパターンはいろいろとありますが、相手が法人か個人事業主かで税金の取扱いが変わってきます。業種によって法人が多い場合、あるいは個人事業主が多い場合など、さまざまなので注意が必要です。
外注先が法人の場合
仕事を外注した相手が法人の場合は特に心配する必要はありません。原則として源泉徴収が不要だからです。法人の場合は業務を受けた外注先が納税します。
例外として「馬主である法人に支払う競馬の賞金」は源泉徴収となりますが、通常の仕事の外注であればあてはまらないでしょう。
外注先が個人事業主の場合
仕事を外注した相手が個人事業主の場合、業務内容によっては源泉徴収が必要です。最近はさまざまな業種で個人事業主と取引している会社が多いのではないでしょうか。源泉徴収するにもさまざまな決まりがあります。
まず個人事業主に対して源泉徴収するかどうかは報酬の種類によって変わります。源泉徴収の対象となるのは以下の報酬です。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇等の芸能、テレビ放送等の出演等の報酬や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
- バンケットホステス・コンパニオンやホステスなどに支払う報酬
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
個人事業主に外注した仕事の報酬が上記に当てはまるなら源泉徴収をしましょう。
参照:国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
外注費とインボイス制度

外注費と給与の大きな違いの中には、上述したように消費税があります。給与には消費税がかかりませんが、外注費の場合は事業者がサービスなどを提供したことに対する対価です。「事業の対価として得る資産」となるため外注費は消費税の課税対象です。
これは外注先が法人でも個人事業主でもかわりません。そして外注費は課税仕入れにあたります。そのため外注で支払った消費税額は仕入税額控除できますので、消費税を納税する際には差し引いて計算します。
ただしここで注意が必要です。2023年10月1日から始まったインボイス制度により、消費税の仕入税額控除ができるのは、インボイス制度に登録している課税事業者からの仕入のみとなります。そのため外注先がインボイス制度に登録しているかが重要です。
法人でも個人事業主でもインボイス制度に登録しておらず、免税事業者のままということも多いでしょう。そうすると消費税の仕入税額控除ができないため、外注費のデメリットの一つである消費税の負担がさらに大きくなります。
外注費が給与と認定された場合の影響
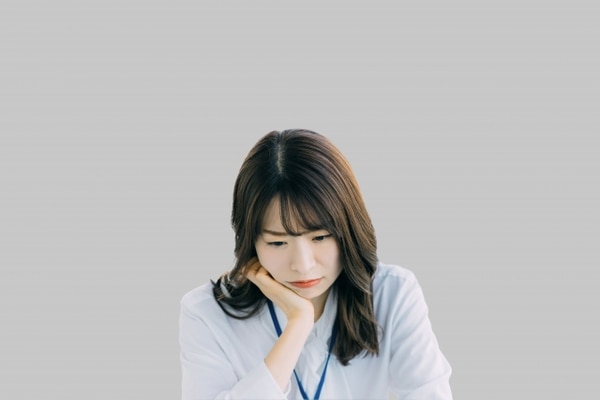
外注費と給与は課税の面でさまざまな違いがあります。もし計上した外注費が実態としては給与であると認定されてしまうと、消費税や源泉所得税、さらには別の税金も課せられる恐れが大きいです。
外注費が給与と認定された場合の影響について解説します。
消費税・源泉所得税の課税
外注費が給与と認定されると、消費税・源泉所得税が発生します。
消費税は課税期間中の課税売上から、課税仕入れにかかった消費税額(仕入控除税額)を差し引いて計算すると解説しました。課税仕入れである外注費を支払うことで仕入控除税額が大きくなるため、納付する消費税額は小さくなります。
しかし外注費ではなく給与と認定されると、外注費部分にかかった消費税がなくなります。課税仕入れにかかった消費税額が小さくなれば消費税の納付額が大きくなるため、すでに納付した消費税額と実際に納付するべき消費税額に差額が生まれてしまうのです。この差額部分について納付が必要です。
また給与の場合、源泉所得税の徴収・納付も行う必要があります。本来給与とするべき支払いを外注費として計上してしまうと、源泉徴収義務者の義務を怠ったとみなされる恐れがあります。また後述する延滞税・加算税の発生リスクもあるため注意が必要です。
延滞税・加算税の課税
外注費が給与とみなされると、その分の消費税・源泉所得税が発生すると解説しました。
これらの税金は、本来給与の支払い時に正しく計上し、期日までの納付が必要であった分です。しかし支払い時に外注費として処理をしており、指摘を受けてから修正をした場合、納税期日を過ぎているケースがほとんどでしょう。
税金の不納付とみなされると、滞納分の税金の支払い義務に加え、延滞税・加算税の納付も必要になります。
延滞税は法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課せられる金額です。支払い遅延に対する利息のような性質を持ちます。原則として納期の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、2ヶ月を経過した日以後は年14.6%が課せられます。
加算税は納税額が正しい金額よりも小さい場合や、納税を怠った場合に課せられるペナルティです。課税割合は10〜40%で、要件によって異なります。
外注費が給与認定されないためには

外注費が給与として認定されてしまうと、税負担の増加やペナルティの発生など、大きな影響が起こります。相手に支払った報酬が外注費と給与のどちらに該当するか判断したうえで、正しい会計処理が必要です。
外注費か給与かを判断するポイントを紹介します。
外注費か給与かを判断するポイント
外注費か給与かを判断するポイントとして、以下の5点が挙げられます。
- 指揮監督の有無や程度:指揮監督の指示に従う必要がある・自由な業務遂行ができない場合、給与に該当する可能性が高いです。ただし業務によっては指揮監督が必須のケースもあるため、総合的・多面的に判断します
- 時間的拘束性の有無:業務の性質上発生しうる拘束時間を除き、時間的拘束性がある場合、給与とみなされる恐れが大きいです
- 報酬の請求権が発生するタイミング:外注費は結果に対して報酬を支払います。納品や業務遂行が完了したタイミングで報酬の請求権が発生する場合は外注費となります。業務時間をもとにした計算・支給の場合は、給与に該当する可能性が高いです
- 代替性の高さ:代替性が高い業務の場合、外注費と認定されるケースが多くなります
- 福利厚生の有無:雇用契約がない場合でも、従業員のように福利厚生制度の権利・取り扱いがある場合、給与とみなされる恐れが大きいです
外注費の仕訳

外注費を支払ったときの仕訳は、支払先が法人か個人事業主かで処理が異なります。それぞれのケースについて具体的な仕訳例を用いて解説します。
法人(源泉徴収が発生しない)の場合
外注費の支払先が法人の場合、源泉徴収が発生しません。そのため発生した外注費の全額をそのまま相手先に支払うことになります。
法人に対して普通預金から20万円を外注費として支払った場合の仕訳は次のとおりです。
借方 |
貸方 |
||
外注費 |
200,000 |
普通預金 |
200,000 |
個人事業主(源泉徴収が発生する)の場合
続いて、外注費の支払先が個人事業主かつ源泉徴収が必要なケースです。
法人と同様、外注費の金額が20万円の場合を例に仕訳例を紹介します。
借方 |
貸方 |
||
外注費 |
200,000 |
普通預金 |
179,580 |
預り金 (源泉所得税等)※ |
20,420 |
||
※源泉徴収税(所得税+復興特別所得税=10.21%)=200,000円×10.21%=20,420円
なお前述したように、外注費の場合は原則として源泉徴収は不要です。源泉徴収が必要となるのは、原稿の報酬など、所得税法で定められた一部の支払いのみとなります。
源泉徴収を行わない場合は、法人に支払うときと同様の処理となります。
また預かった源泉徴収税は、外注費の支払い相手に代わって企業側で納付が必要です。税法のルールに従って正しく納税を行いましょう。
まとめ

外部の会社や個人に業務の一部を委託すれば、自社にない技術やノウハウを活用することができ、事業活動を円滑に進められます。外部に委託をした際に支払う報酬は、一般的には外注費として処理が必要です。
しかし、委託先が事業者ではなく自社の指揮監督の下で仕事を進めていたような場合は、給与と判断される場合があります。経理処理を行う勘定科目が異なれば、所得税や消費税など税金に関わる部分の計算にも違いが出てくるので注意が必要です。
ときには外注費と給与の判断が難しいケースも有り得るでしょう。適切な経理処理を行うためには、当事者ですべて対応しようとせず、専門家に依頼するのがおすすめです。
グランサーズ株式会社が運営するオンラインアシスタント・秘書サービスの『SUPPORT+iA(サポーティア)』は、総務、経理、人事、労務などのバックオフィスの業務をオンラインでサポートしています。公認会計士が監修しているクオリティの高さが強みです。
正確で効率的な経理業務を実現するためにも、是非サポーティアをご利用ください。
関連記事