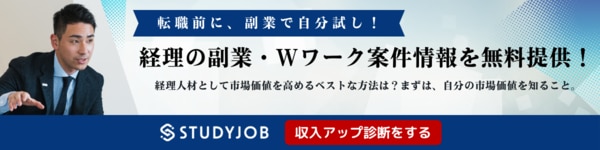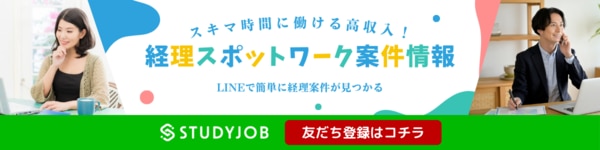アルバイトも源泉徴収の対象になる?源泉徴収が必要になる条件や注意点についてわかりやすく解説
オンラインアシスタント・秘書サービスなら「サポーティア(SUPPORT+iA)」
正規雇用の社員に支払う給与は、全額そのまま支給するわけではなく、所得税や社会保険料などを天引きした額を支払います。一方でアルバイトとして雇用している従業員の場合、給与全額を支給するケースも多いです。そのためアルバイトの給与からは、何も天引きする必要がないと感じるかもしれません。
しかしアルバイトであっても、ケースによっては所得税を天引きする源泉徴収の対応が必要です。本記事では源泉徴収の対象となるアルバイトの条件や、源泉徴収の注意点などを解説します。
目次[非表示]
そもそも:源泉徴収とは?

アルバイトの源泉徴収について具体的に見る前に、まずは源泉徴収の意味や仕組みについて改めて解説します。
源泉徴収とは、給与から所得税を天引きする行為です。所得税は1年あたりの所得額に対して課せられる税金のため、年間の給与額の合計が明確になるまで所得税の正確な金額はわかりません。しかし1年分の所得税をまとめて支払うのは、大きな負担となってしまいます。そこで概算で算出した所得税を、毎月の給与から天引きする形で徴収します。これが源泉徴収です。
なお前述したように源泉徴収で天引きした所得税は、あくまで概算によるものです。そのため年間の給与額が明確になったら正しい所得税を算出し、必要に応じて過不足の精算を行う必要があります。この作業を年末調整といいます。
※厳密には年末調整にあたって給与以外の情報も必要ですが、本記事では源泉徴収をメインに解説するため詳しい内容は省略します。
アルバイトにも源泉徴収を行う必要がある

正社員には源泉徴収を実施するものの、アルバイトとして雇用している従業員に対しては、給与全額をそのまま支給するケースも多いのではないでしょうか。確かにアルバイトという雇用形態の場合、源泉徴収が必要ないパターンが少なくありません。
しかし雇用主には、従業員の雇用形態に関係なく源泉徴収を行う義務があります。そのため本来はアルバイトに対しても源泉徴収を行う必要があります。
ただしアルバイトの場合、源泉徴収が必要となるほどの給与額に達しないケースが多いです。そのような従業員の場合、所得税の天引きをせず給与額をそのまま支給します。
源泉徴収をしないのは「アルバイトだから」ではなく、「源泉徴収が必要となる給与額ではないから」です。雇用形態は関係ない点に注意しましょう。
源泉徴収の必要がない具体的な要件は後述します。
源泉徴収の必要がないアルバイトとは?

源泉徴収は給与が一定額を超える従業員に対して義務付けられています。言い換えると、給与額が基準よりも低ければ源泉徴収が必要ないということです。
それでは源泉徴収の必要がないアルバイトについて、具体的に解説します。原則として、月給88,000円未満の場合は源泉徴収が不要です。アルバイトに限らず月給88,000円未満の従業員は、源泉徴収の対象外となります。
また年収が103万円以下の場合、所得税は発生しません。給与が88,000円以上で源泉徴収をした月があったものの、年間給与額が103万円以下であれば、天引きした額を年末調整で還付する必要があります。
アルバイトの源泉徴収に関する注意

アルバイトとして雇用している従業員でも、要件を満たす場合は源泉徴収が必要です。しかしアルバイトに対する源泉徴収は、他の雇用形態よりも注意が必要なポイントがあります。アルバイトの源泉徴収に関する注意点を紹介します。
アルバイトに源泉徴収の必要性を説明しておく
源泉徴収がはじめてのアルバイトには、給与支給前に源泉徴収について説明しておくと安心です。給与から所得税が天引きされている旨と、源泉徴収が必要な理由の説明を行いましょう。
特に学生アルバイトなどの場合、源泉徴収という仕組みを知らない場合も多く、働き始めてはじめて知るというケースが一般的です。そのため源泉徴収についてまったく知らない状態で、いきなり給与額から所得税が引かれていたら驚いてしまいます。「何の説明もなく給与から税金が引かれてる」と不信感を持たれてしまい、トラブルの元になる恐れもあります。源泉徴収の存在を知っていても、これまで天引きされた経験がなかった人であれば、やはり驚いてしまいます。
こういったトラブルは、源泉徴収について事前に説明すれば防げるものです。源泉徴収は給与計算の担当者には馴染み深いものかもしれませんが、アルバイトにとっては違います。源泉徴収について事前に説明しましょう。
甲・乙・丙の税区分に注意
月の給与額が88,000円未満の従業員は、原則として源泉徴収の必要がないと紹介しました。しかし厳密にいうと、働き方や書類提出の有無などによっては、給与額が小さくても源泉徴収が必要なケースがあります。源泉徴収の条件や天引きする税額は、甲・乙・丙という3パターンの税区分によって異なります。
甲とは従業員が事業所に「扶養控除等申告書」という書類を提出している場合に適用する税区分です。甲欄の従業員は、先ほど解説したように月額88,000円未満であれば源泉徴収が必要ありません。
乙は「扶養控除等申告書」を提出していない従業員の税区分です。扶養控除等申告書は一箇所にしか提出できないため、掛け持ちで働いている場合、主たる勤務先以外では乙欄を適用します。乙欄の場合、給与額が88,000円未満の月も源泉徴収が必要です。アルバイトとして働く人は掛け持ちしているケースも多いため注意しましょう。
丙は日雇いや短期雇用(2ヶ月以内)の従業員に用いる税区分です。書類提出や扶養の有無などに関係なく適用されます。
アルバイトの税区分によって、源泉徴収が必要となる条件や税額が異なるので注意が必要です。なおそれぞれの税区分で徴収する税額は、「源泉徴収税額表」に明記されているのでご確認ください。
源泉徴収票を必ず発行する
アルバイトであっても、源泉徴収票を必ず発行します。
源泉徴収票とは年間の給与額や所得税額を記載した書類です。雇用形態に関わらず、すべての従業員に対して発行が義務付けられています。給与額が小さく所得税の天引きを一切行っていないアルバイトに対しても必要です。
源泉徴収票の発行が必要なタイミングは大きく2つあります。
年間の給与額が明確になったタイミング(その年の12月に給与明細と一緒に送付するケースが多いです)
従業員が退職した場合(年の途中に退職した従業員にも発行が必要です。最後の給与明細と一緒に送付、もしくは年末に送付するケースが一般的です)
源泉徴収票の発行は雇用主の義務です。源泉徴収の有無に関わらず、アルバイトを含むすべての従業員について、必ず源泉徴収票を発行しましょう。
源泉徴収を行ったアルバイトの年末調整

年末になると源泉徴収を行ったアルバイトも含めて、雇用している人の年末調整をします。1年の収入が確定した時点で、源泉徴収した所得税を調整するために必要な手続きです。
アルバイトで年末調整ができる人の条件を見ていきましょう。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している
年末調整をするためにはアルバイトに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう必要があります。源泉徴収税額の計算に必要な情報が記載してあるため、この書類がなければ正しい所得税を計算することができません。
扶養親族や源泉徴収対象配偶者などがいない人も提出する必要があります。もし提出がない場合は、前述の税額表の「乙」欄が適用された源泉徴収税額となります。
12月末にアルバイトが在籍している
12月末の時点で、アルバイト本人が会社に在籍していることが重要です。1月から働いている必要はなく、1年の途中からの入社でもかまいません。もし退職が決まっていても、12月末までの在籍なら年末調整を行います。
また別の会社で働いていたアルバイトが以前の勤務先での源泉徴収票を持っている場合は、自社の12月末までの源泉徴収と合わせての年末調整が可能です。
複数の仕事を掛け持ちしているアルバイトは主たる会社のみ
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、年末調整ができるのは主たる会社のみで、それ以外の会社では年末調整ができません。そのため主たる会社以外の会社も含めて源泉徴収票をもらい、確定申告をします。
掛け持ちアルバイトの源泉徴収は?

アルバイトを掛け持ちしている人の場合、所得税の源泉徴収はどうなるのでしょうか。払いすぎていることがあるかもしれません。それぞれのアルバイト先で源泉徴収されていることも考えられます。
まず1つのアルバイトだけをしている人と、掛け持ちでアルバイトをしている人では税区分が違います。上で述べたように源泉徴収の条件や天引きする税額は、甲・乙・丙という3パターンの税区分です。
1つのアルバイトだけをしている人は「甲」の区分になるので、月額88,000円以下は源泉徴収されず、超えた場合は「甲」欄の税額で源泉徴収されます。さらに扶養控除等申告書を出せば、年末調整も可能です。
一方、アルバイトを掛け持ちしている人は、それぞれの会社の扱いによって税区分が分かれます。
多くの給与をもらっている主たる会社は「甲」の区分です。そのため上記のように月額88,000円で源泉徴収されるかどうかが分かれます。もし源泉徴収されたとしても、年末調整を行うことで税が還付されるかもしれません。
主たる会社以外では「乙」の区分になります。年末調整の対象にもならないため確定申告が必要です。ただし主たる会社以外の年収が20万円以下であれば確定申告は任意となります。
しかし「乙」の税区分では月額88,000円未満の月も源泉徴収が行われているので、収入によっては確定申告で税の還付が受けられます。
源泉徴収されているアルバイトの確定申告は?

アルバイトをしている人の中には確定申告をした方がいい人もいます。源泉徴収している税金が還付される可能性があるからです。
源泉徴収されているアルバイトで確定申告が必要な人
源泉徴収されているアルバイトで確定申告が必要な人はさまざまなパターンがあります。
- アルバイトは1つだけで扶養控除等申告書を提出せず年末調整を行っていない人
- アルバイトを掛け持ちしていて、年末調整を1社でしか行っていない人
- アルバイトはしていたが年末にはどこにも在籍していなかった人
これらのアルバイトの人で源泉徴収されていれば、確定申告をするのがおすすめです。収入が103万円以下でも源泉徴収されている可能性があります。確定申告をすれば払いすぎた税金が返ってきます。
アルバイトが確定申告をする時は?
確定申告をする必要がある場合は、確定申告をできる期間が決まっていること、必要な書類があることなどを知っておく必要があります。
まず確定申告をするのはアルバイト先の会社ではなく本人です。必要な書類などの手配もアルバイト本人がします。
■確定申告期間
毎年1月初旬~3月中旬に行われます。後述する申告方法によって開始時期が変わりますので注意が必要です。
■確定申告の方法
確定申告は国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署で作成、作成した申告書を郵送、ネット上で提出するe-Taxなどの方法があります。
ただ確定申告書等作成コーナーや税務署に出かけて行って作成する人が多いため、たいへん込み合います。相談に乗ってもらいながら作成できるので、不安がある人にはいいですが、自分で申告書の作成ができそうな人は避けた方がいいでしょう。
e-Taxであればスマートフォンでの作成も可能で、1月初旬から申告の受付がスタートするのでおすすめです。
■確定申告に必要なもの
源泉徴収票は現在働いているすべての会社のものが必要です。また現在は働いていない会社のものも必要となります。それぞれの会社に依頼して確定申告までに源泉徴収票を用意します。
控除に必要な書類も用意します。例えば社会保険(国民健康保険・国民年金)の控除証明書、加入している生命保険などの控除証明書、勤労学生控除を受けるなら在学証明書などです。もし多くの税金が源泉徴収されているなら控除できるものがあれば、還付される金額も大きくなるかもしれません。
e-Taxを利用する場合はマイナンバーカードが必要です。スマートフォンでマイナンバーカードを読み取りますが、場合によってはカードリーダーも必要ですので、確認しておいた方がいいでしょう。
アルバイトの源泉徴収をしないとどうなる?
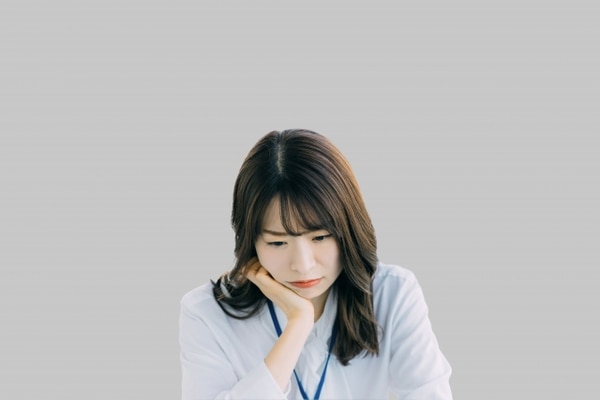
アルバイトの源泉徴収をしないでいると、所得税の不納付と認定されてしまいます。納税を怠ると、以下のようなペナルティが課せられる恐れがあります。
-
延滞税:
納期限の翌日〜2ヶ月は、納付するべき税額の7.3%(年) 以降は14.6%(年)
-
不納付加算税:
納期限を過ぎてから自主的に納付する場合は納付するべき税額の5% 指摘を受けてから納付する場合は10%
アルバイトの源泉徴収をしないことによるペナルティは非常に重いです。また単純に延滞税・加算税による金銭的負担を受けるだけでなく、納税義務を怠った事業所として税務署に目をつけられてしまう可能性もあります。
アルバイトなどの雇用形態に関係なく、すべての従業員に対して必ず源泉徴収を行いましょう。
まとめ
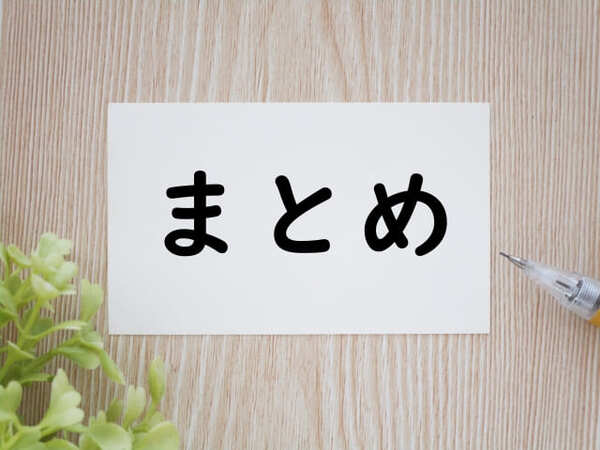
源泉徴収の必要有無は、原則として月の給与額によって変わります。アルバイトは源泉徴収を行わないケースも多いですが、雇用形態による理由ではありません。勤務時間が短く給与額が小さいため、源泉徴収の対象外となるケースが多いだけです。
源泉徴収は一定の給与額を超えるすべての従業員に対して行う必要があります。源泉徴収の意味や必要性をしっかり理解し、アルバイトに対しても適切に実施しましょう。
源泉徴収でお悩みのときは、グランサーズにご相談ください!

源泉徴収についてお悩みのベンチャー企業は、オンラインアシスタントやアウトソーシングサービスの利用も検討してみてはいかがでしょうか。
『グランサーズ株式会社』では、自社で運営しているオンラインアシスタントやアウトソーシングによって、スタートアップ企業やベンチャー企業の支援を行っています。どちらのサービスも公認会計士が監修しているクオリティの高さが強みです。
オンラインアシスタント・秘書サービスの『SUPPORT+iA(サポーティア)』は、総務、経理、人事・労務などのバックオフィスの業務をオンライン上でサポートして、業務効率化に貢献してくれます。
アウトソーシングでは、バックオフィス業務を専門性の高いスタッフが代行してくれます。優秀な人材が会社に常駐してくれるので、いつでも依頼や相談ができますよ。ぜひ活用してみてください。
関連記事