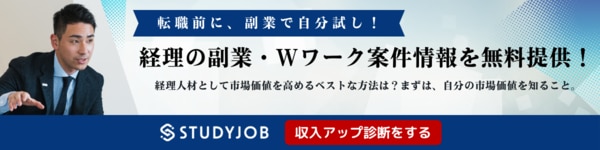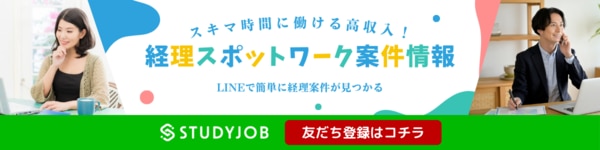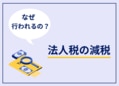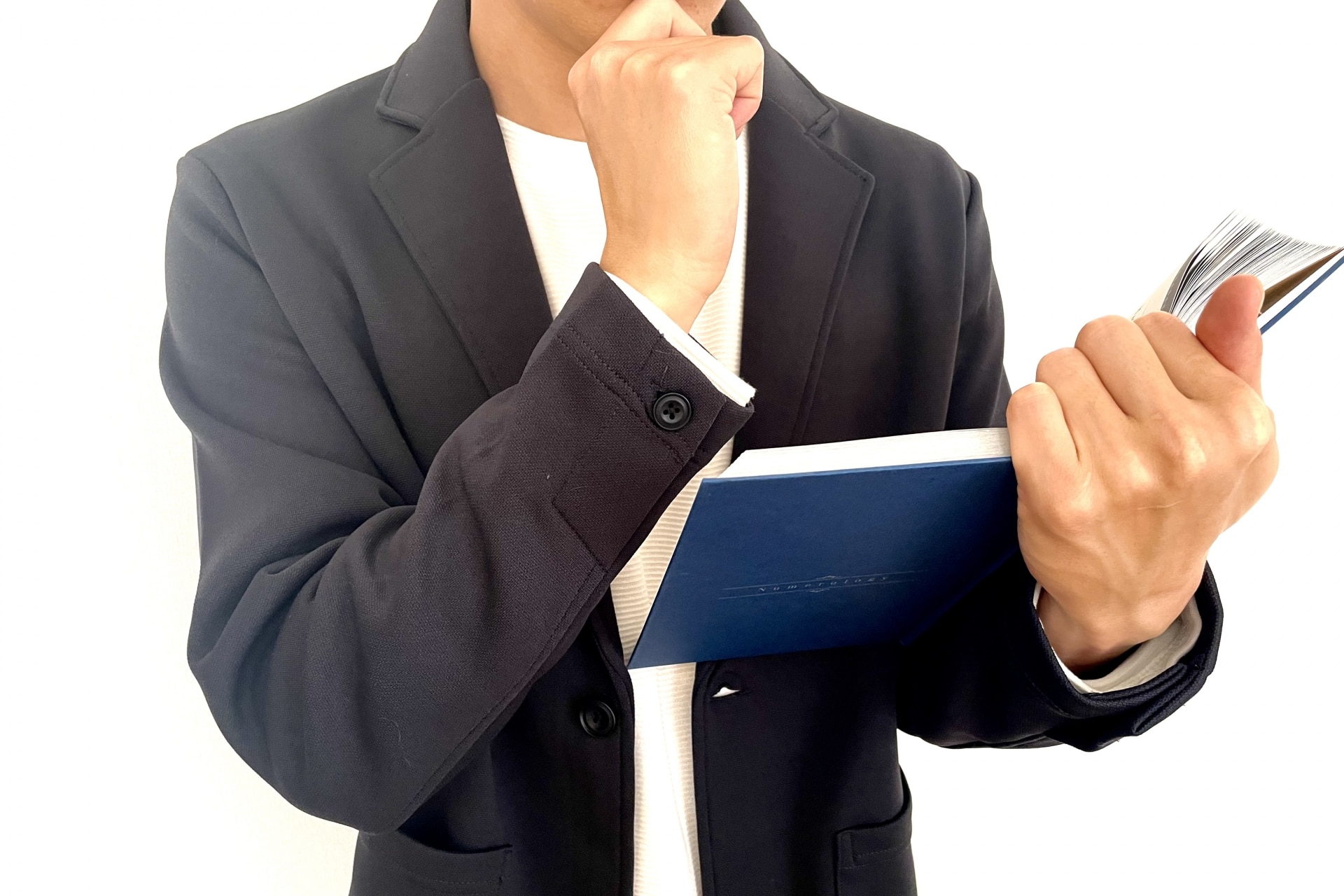
【知らなきゃ損!】法人税が免除される条件は?消費税も2年間免除が可能
オンラインアシスタント・秘書サービスなら「サポーティア(SUPPORT+iA)」
株式会社などの法人は、事業活動を通じて利益を得ると法人税を納める必要があります。法人が納める税金の種類を把握して、どのような場合に税金を納めるのかを理解しておきましょう。
一方で、赤字決算となる場合は法人税が免除されます。条件を満たせば消費税も2年間の免除が適用されます。この記事では、法人税や消費税が免除される条件について詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.法人税の基本
- 1.1.法人税と実効税率
- 1.2.税制上の措置について
- 2.法人税の支払いが免除されるケース
- 2.1.法人税法上の所得が赤字(マイナス)の場合
- 2.2.赤字でも免除されない税金
- 2.3.法人税の計算における注意点
- 3.欠損金の繰越控除
- 3.1.赤字の場合は翌年に繰越
- 3.2.翌年黒字の場合は控除
- 3.3.10年間の繰越期間が認められている
- 4.欠損金の繰戻し還付制度
- 5.消費税の免除
- 6.新型コロナウイルス感染症における措置
- 7.法人税が免除されるケースを把握して税負担を軽くしよう
法人税の基本

法人税とは、法人が事業活動を通じて得られた所得に応じて課せられる国税です。
法人税は原則として決算日の翌日から2ヶ月以内に、申告および納税を行う必要があります。たとえば法人の決算日が3月31日である場合、法人税の申告および納税の期日は5月31日です。
法人税の申告・納付先は、事務所の本店所在地を管轄する税務署となります。納付方法は4つあり、それぞれ異なるメリット・デメリットを持つため、自社に合った方法を選びましょう。
- 現金納付:金融機関や税務署の窓口で納付する方法です。職員に直接確認できるため誤りのリスクを抑えられます。ただし窓口へ出向く手間がかかります。納付金額が30万円以下の場合、バーコード付納付書やQRコードを用いてコンビニエンスストアでの納付も可能です
- クレジットカード納付:クレジットカードのポイントが貯まる一方、納付金額に応じて手数料も発生します。また領収書は発行されません
- ダイレクト納付:事前にe-Taxの設定をすることで、口座からの自動振替による納税が可能です
- インターネットバンキング納付:ダイレクト納付と同様、事前にe-Taxの設定が必要です。領収書は発行されません
法人税と実効税率
前述したように、法人税は法人の所得に対して発生する国税です。法人税の税率は法人の種類・規模・所得額によって定められています。たとえば資本金1億円以下の普通法人の場合、所得のうち年800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分には23.20%の税率が適用されます。
しかし法人の所得にかかる実質的な税額を計算する際、所得に法人税率を乗じるだけでは不十分です。実際に発生する税額を算出する場面では、実効税率を用います。
法人税の実効税率とは、法人の実質的な税負担率を指します。
法人の所得にかかる税金は法人税だけではありません。法人住民税や事業税などの税金も所得に対してかかります。したがって法人の所得額に法人税率を乗じただけでは、所得にかかる実際の税額と大きく乖離する恐れがあるのです。
法人の所得に対してかかる税の合計を知るためには、実効税率を用いる必要があります。
税制上の措置について
税制上の措置を示す言葉として、免除・猶予・優遇・減免が挙げられます。それぞれの意味は以下のとおりです。
税制上の措置 |
言葉の意味 |
免除 |
納税義務がなくなるので、税金を納める必要がない |
猶予 |
一定の条件を満たすことで、期限内に納めるべき税金の納付期限を後ろ倒しにできる |
優遇 |
一定の条件を満たせば、税額が引き下げられる、中小企業の税制優遇等 |
減免 |
税金を軽減または免除するという意味。災害時による減免制度など |
税金の計算においては、納めるべき税金の種類や税額を把握するだけでなく、どのような場合に税制上の措置がとられるのか正しい理解が必要です。
法人税の支払いが免除されるケース

法人税の支払いが免除されるケースとして、法人税法上の課税所得がマイナスとなる場合があげられます。
ただし赤字であっても、法人にかかるすべての税金が免除されるわけではありません。免除されるものとそうではないものをしっかり把握する必要があります。
法人税法上の所得が赤字(マイナス)の場合
法人が事業活動を通じて得た所得が赤字となる場合、法人税は免除されます。
ただし、企業会計は赤字であっても、法人税法上の課税所得がある場合は法人税が免除されない点に注意が必要です。
企業会計では「収益-費用」で利益額が決まりますが、税務会計においては「益金-損金」で所得額が決まります。収益と益金、費用と損金は同一ではないため、企業会計上の決算が赤字だからといって税法上も所得がマイナスになるとは限らないのです。
企業の活動としてかかった経費を費用として計上できますが、それらの費用のすべてが損金として認められるわけではありません。
法人税が免除となるかどうかは、法人税法のルールに沿って計算したときに把握できます。税理士に相談したうえで納税の有無を判断しましょう。
赤字でも免除されない税金
法人税が免除となった場合でも、そのほかの税金が赤字を理由に免除されるわけではありません。課税所得がマイナスとなっても支払う税金として、「法人住民税の均等割」と「消費税」があげられます。
法人住民税の均等割は、赤字であっても必ず納める必要のある税金です。東京都の場合は資本金が1,000万円以下で従業員数が50人以下の中小法人であれば7万円となっています。均等割の額は事業所の所在する自治体によって異なるため、詳しくは自治体のホームページなどでご確認ください。
また、消費税はいわゆる預かり税と呼ばれるものです。事業者が顧客から預かった消費税は、仕入れとして支払った消費税を差し引いて納税する必要があります。
赤字決算となる時期は、企業としても資金繰りが悪化しやすいタイミングです。赤字でも納める税金があることを正しく把握して、納税時に困らないように準備しておきましょう。
法人税の計算における注意点
法人税の計算にあたって注意したいポイントとして、損金と費用の違いが挙げられます。法人税の損金には含まれない会計上の費用があるのです。これについて詳しく解説していきます。
法人税の計算で用いるのは法人税法上の課税所得です。そして前述したように、企業会計上の利益と法人税法上の課税所得は一致するとは限りません。企業会計で用いる収益・費用と、税務会計で用いる益金・損金は同一ではないためです。
会計上は費用であっても、税法上の損金に含まれない支出として、以下の例が挙げられます。
- 交際費:一定の要件を満たしたもの以外は原則として損金不算入です。また損金不算入できる金額には上限もあります
- 役員報酬:役員報酬の原則として損金不算入です。損金にするには細かなルールを守る必要があります
- 寄付金:寄付金には上限が設定されており、上限を超えた分については損金不算入です
- 減価償却超過額:減価償却費にも損金にできる上限額が決められています
- 一部の租税公課:延滞税・罰金・過料・違反金も損金不算入です
法人の所得を正しく計算するためには、税法上の損金について正しく理解する必要があります。
欠損金の繰越控除
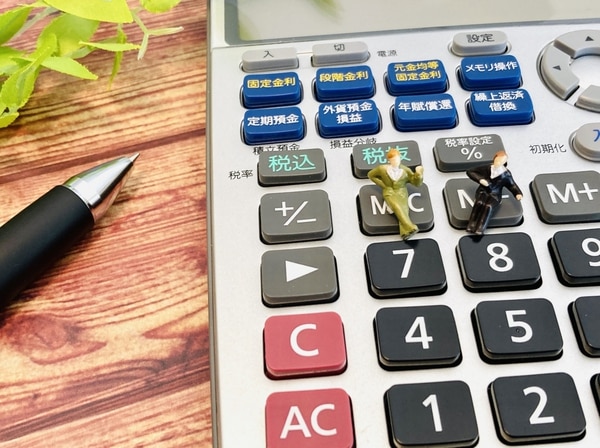
欠損金とは、法人税を計算する際に所得が赤字となった部分を指します。青色申告の承認を受けている法人では、欠損金を一定期間繰り越して、将来の黒字分と相殺が可能です。
2018年(平成30年)以降に開始する事業年度からは、欠損金の繰越期間が10年間となっています。資本金が1億円以下の中小企業では繰越欠損金の全額が認められている点を押さえておきましょう。
欠損金の扱いについて、所得が赤字であった場合・黒字であった場合、それぞれについて解説します。
赤字の場合は翌年に繰越
税務会計上の所得が赤字となる場合、欠損金は翌年以降への繰り越しが可能です。前述したように、繰り越された欠損金は将来の黒字分と相殺できます。そのため、赤字部分の金額が大きいほど、翌年以降の税負担が軽くなる可能性が高いです。
赤字や黒字をすべて意図的にコントロールできるわけではありませんが、繰越欠損金の有無や大きさは、翌期以降の経営を見通すうえで役立ちます。
翌年黒字の場合は控除
前事業年度が赤字で欠損金が発生し、その翌年が黒字であった場合には、その期の黒字と過去の赤字を相殺できます。法人税の課税対象になるのは、相殺した後の黒字部分のみです。したがって欠損金による相殺分が大きいほど、税負担は軽減されます。
また、黒字額よりも赤字額が大きければ、その年の法人税は発生しません。相殺しきれず残った欠損金については、その翌年以降も繰越欠損金として処理できます。
10年間の繰越期間が認められている
欠損金の繰越期間として、以前は9年間と設定されていました。しかし2016年(平成28年)の税制改正によって欠損金の繰越期間が1年延長され、2018年以降は10年間の繰越が認められています。
税制改正は頻繁に行われるものであり、欠損金の繰越期間が今後も10年間のままとは限りません。最新の税制に沿った正しい会計処理・税額計算ができるよう、国税庁のホームページなどで最新情報を把握しておきましょう。
欠損金の繰戻し還付制度

税務会計上の所得が赤字となった場合、赤字は欠損金として扱われます。欠損金は10年間の繰越期間が設定されており、翌期以降の黒字と相殺できると紹介しました。
一方で中小企業者等が赤字となり欠損金が発生した場合、過去の黒字に際して納付した法人税の還付を受けられるケースがあります。その際に用いるのが、欠損金の繰戻し還付制度です。
欠損金の繰戻し還付制度について詳しく解説します。
中小企業・個人事業主は赤字の場合に遡って還付を受けられる
欠損金の繰戻し還付制度とは、中小企業・個人事業主といった中小企業者等のみが利用できる制度です。欠損金が発生した事業年度の前期(全事業年度)が黒字であった場合、前期に納付した法人税の一部または全額の還付を受けられます。
欠損金の繰戻し還付制度を受けるための要件は以下の3つです。
- 前期および当期の連続した青色申告の確定申告書を提出している
※前期に法人税の申告を行なっていない場合は欠損金の繰戻し還付制度の適用を受けられません - 当期の決算申告を期日までに行なっている
- 当期の決算申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出する
還付を受けられる金額は以下の算式で計算します。
前期の法人税額×(当期欠損金額/前期所得金額) |
なお計算式に含まれている「当期欠損金額」は、前期の所得金額が上限です。当期の欠損金額が前期の所得金額を上回っている場合、上回る分は通常のように欠損金の繰越対象となります。
消費税の免除

消費税は商品やサービスを購入したときに課せられる税金ですが、事業者が直接負担するものではありません。消費税は間接税と呼ばれる、負担者と納税者が異なる税金です。
また消費税は売上の発生時などに消費者から受け取るだけではなく、事業者自身も仕入れや各種サービスの利用などで支払うことになります。消費者から預かった消費税額から事業者が支払った消費税額を差し引いた金額を、消費税として納める必要があります。
このように消費税は法人の所得額とは関係なく、決算が赤字の場合でも納める必要があるため、注意が必要な税金だといえるでしょう。
一方で、特定の条件を満たす場合には消費税が免除されることがあります。法人の消費税が免除となる条件について詳しく解説します。
資本金1,000万円未満であれば一期目は消費税免除
消費税が免除となるケースのひとつが、資本金1,000万円未満の法人設立直後です。法人の資本金が1,000万円未満であれば、一期目は条件を問わず消費税が免除となります。
税法上の措置で紹介したように、免除とはそもそも納税義務がない状態です。したがって消費税の申告も必要ありません。また消費税に関する決算整理仕訳など、会計処理・記帳作業も不要です。
ニ期目も消費税が免除になる条件とは
二期目も消費税が免除になるケースもあります。消費税の免除対象になるには、以下2つの要件をどちらも満たす必要があります。
- 資本金が1,000万円未満である
- 以下いずれかの要件を満たす
・1期目の上半期の課税売上高が1,000万円以下である
・同期間の給与等の支払総額が1,000万円以下である
消費税が免除となる条件をまとめると、以下のようになります。

気になる場合は最寄りの税務署に相談をしてみましょう。
新型コロナウイルス感染症における措置

新型コロナウイルスの感染拡大によって、さまざまな業種で経営環境が悪化している傾向が見られます。厳しい経済環境の中にあって、日本においても緊急経済対策として、税制上の優遇措置が数多くとられています。優遇措置や制度の活用によって、税負担の軽減が期待できるでしょう。
たとえば「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」として、中小企業がテレワークなどを行う上での税制上の優遇措置がとられています。具体的には、中小企業経営強化税制の対象に組み入れられており、設備投資の一定額を税額控除することが可能です。
また新型コロナウイルス感染症に関連して、生活困窮者への支援として自社商品の無償提供を行なった場合、発生した金額は損金計上できると国税庁が公表しています。寄付金は損金算入できる上限額が設定されていますが、このようなケースの支出は寄付金とは異なる扱いです。ただし感染症の流行が終息するまでという限定的な内容ではあります。
税制上の優遇措置のほか、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱いについては国税庁の公式サイトで詳しく案内されています。
法人税が免除されるケースを把握して税負担を軽くしよう

法人税は事業活動を続けていれば、基本的に納めるべき税金です。しかし、決算が赤字となる場合には納税が免除され、青色申告の承認を得ていることで欠損金として翌年以降にも赤字額を繰り越せます。法人税が免除されるケースを把握し、仕組みを上手く活用して税負担を軽くしましょう。
とはいえ赤字決算が続くことは、経営において大きなマイナスです。税負担の軽減ばかりを優先せず、早期の黒字化も求められます。法人税の免除を利用できる場合は当然利用するべきとはいえ、積極的に狙うのはリスクが高いため注意が必要です。
税負担を軽減するには、日頃から正しく会計処理を行っておくことが重要です。オンラインアシスタント・秘書サービスの「SUPPORT+iA(サポーティア)」では経理などバックオフィス業務をサポートするサービスを数多く提供しているので、ぜひ活用してみてください。
関連記事